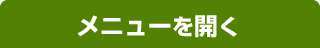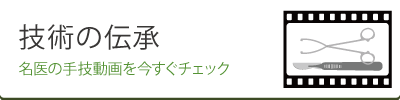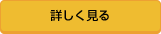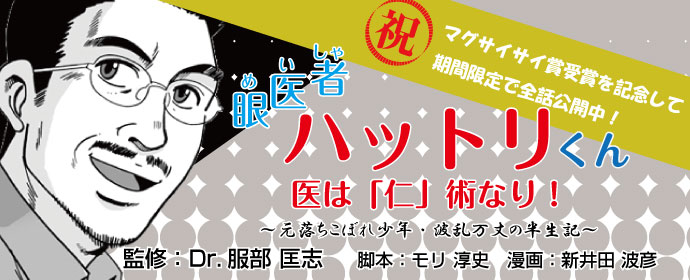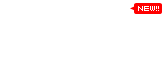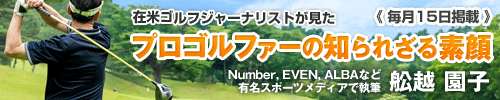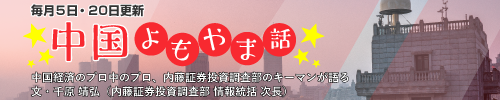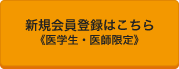おすすめコンテンツ
専門サイトから注目の記事を配信2024/10/22 更新 | ニュース一覧
-
2024/10/22
「病院船」運用へ本格準備、民間カーフェリーで実動訓練…大規模災害時に海上から医療アプローチ
「病院船」運用へ本格準備、民間カーフェリーで実動訓練…大規模災害時に海上から医療アプローチ(医療ニュース)
政府は来年度から、医療機材や病床を備えた「病院船」の運用に乗り出す。震災など大規模災害が発生した際、入院患者の搬送やけが人らの治療を担い、現地の病院を支援する。当面は民間のカーフェリーを活用する方針で、今月には実動訓練を行い、実用化に向けた準備を本格化させた。
内閣官房によると、病院船は被災地近くの港に接岸し、現地の病院の入院患者を離れた地域に移送したり、軽傷者らを船内で治療したりして、陸上の医療機能を補完する役割を持つ。手術室がないことなどから、重傷者には対応できない。
米国では、1000床のベッドを備える海軍の病院船「マーシー」が、2004年のインドネシア・スマトラ島沖地震で出動した。新型コロナウイルスの流行時には、肺炎以外の患者の療養に使われた。
国内では、1995年の阪神・淡路大震災以降、導入が議論された。その後、東日本大震災など災害が相次いだことを受け、病院船の活用を定めた「災害時船舶活用医療提供体制整備推進法」が2021年6月、議員立法で成立した。
同法には病院船を保有することが定められたが、20年度の試算では、500床規模を新造すると約430億円かかる。このため、将来的な保有を前提に、まずは民間のカーフェリーを借りて運用し、必要な機材や設備などを見極める。
運用を担う内閣府が複数の船舶会社に協力を要請。災害時に使用料を支払ってカーフェリーを借りることを想定している。船には日本赤十字社の医師らが乗り込み、日赤の医療機材を持ち込む。普段は車を止めるスペースに並べたテントや客室を病床とする。
今月14日には、北海道・室蘭港で実動訓練が行われた。「DMAT」(災害派遣医療チーム)などに所属する約30人の医療従事者が参加し、フェリーに救急車が乗り入れる流れなどを確認した。結果を踏まえ、政府は、年度内に出動や活動の手順をまとめる。
能登半島地震のように、港の地盤が隆起して座礁の恐れがある場合は接岸できず、活動できないケースもある。厚生労働省内には、巨額の建造費をかけ、病院船を保有することを懸念する声も出ている。
災害時の医療に詳しい日赤の災害医療統括監の丸山[全文を読む] -
2024/10/22
臓器移植で緊急性の高い患者を優先するルール、対象を肝臓のみから「心臓・肺」に拡大へ
臓器移植で緊急性の高い患者を優先するルール、対象を肝臓のみから「心臓・肺」に拡大へ(医療ニュース)
脳死者から提供された臓器の移植を受ける患者を選ぶ基準について、厚生労働省は、命の危険が迫り、緊急性が高い患者を優先するルールを拡大する検討に入った。肝臓だけでなく、心臓や肺に広げる。移植が間に合わずに亡くなる患者を減らす狙いがある。月内にも開く厚生科学審議会の臓器移植委員会で議論を始める。
脳死者から提供された臓器については、日本臓器移植ネットワーク(JOT)が厚労省の基準を踏まえて、移植を待つ患者の優先順位を決める。上位から、患者が登録した移植施設に臓器の受け入れを要請する。基準は、学会や研究会の提案を反映しており、臓器で異なる。
見直しは心臓移植から始める。現在は待機期間が長い患者が移植を受けやすい基準になっている。同委員会では、余命が短いと判断された患者については待機期間にかかわらず最優先に臓器をあっせんできないかや、対象となる患者の具体的な条件を議論する。肺移植でも検討したい考えだ。すでに肝臓では余命が1か月以内の患者に適用している。
このほか、心臓や肝臓などで臓器を摘出する施設と近距離の移植施設に登録する患者の優先度を高める案も検討する。両施設が離れているため、臓器の搬送を担う人員や手段が確保できず臓器の受け入れを断念する場合がある。搬送時間の短いケースを優先させることで、断念を防ぐことが期待できるとする。
JOTによると、9月末現在、国内の待機患者は1万6452人。23年は592人が移植を受けた一方、463人が待機中に亡くなった。
移植を受ける患者の選定基準の見直しは、より多くの命を救うためだ。
具体的な検討に入る心臓は、移植を受ける患者の待機期間が長期化し、平均5年を超えている。現行基準では、待機中に病状が悪化しても優先されず、命を落とす患者が後を絶たない。
厚生労働省が9月に公表した移植の実態調査では、一つの臓器あっせんで多くの患者が移植を見送られていた現状が判明した。効率的なあっせんが行われていないとして、移植医療体制の改革案に盛り込まれた。
今後、臓器摘出の施設と移植施設の近さを優先する案も議論される見通しだ。
[全文を読む] -
2024/10/22
国産手術支援ロボ「ヒノトリ」で11歳男児の腫瘍摘出に成功、出血はごく少なく経過良好
国産手術支援ロボ「ヒノトリ」で11歳男児の腫瘍摘出に成功、出血はごく少なく経過良好(医療ニュース)
神戸大病院は17日、国産初の手術支援ロボット「hinotori(ヒノトリ)」を使って、小学生男児(11)の副腎腫瘍を摘出する手術に成功したと発表した。ヒノトリで15歳未満の小児を対象に手術を行ったのは初めて。経過は良好という。
発表によると、男児は関西在住。6月にけいれんなどを発症して別の病院に入院し、腎臓の上にある副腎にできる希少な腫瘍「褐色細胞腫」と診断された。
ヒノトリは、川崎重工業とシスメックスが共同出資するメディカロイド(神戸市)が開発した。ロボット支援手術は患者の出血量が少ないのが利点で、2020年に製造販売が承認され、今年6月末現在、全国の医療機関に61台導入されている。
手術器具を取り付けるアームが比較的細く、先行する米国製の手術支援ロボットよりもアームの関節数が多いことから小回りが利き、体の小さな患者でも操作しやすいのが特長という。
手術は9月18日に行われ、左右にある副腎のうち、腫瘍が見つかった右側を摘出した。4本あるアームのうち3本を使用してごく少ない出血で済み、男児は同月下旬に退院し、通学できるほどまで回復している。
執刀した神戸大病院小児外科の大片祐一・特命准教授は「小児外科の手術で、日本製ロボットの選択肢を加えることができた。質の高いロボット手術を提供する体制を整えていきたい」としている。[全文を読む] -
2024/10/09
マイコプラズマ肺炎、8年ぶり流行…専門家「人混みでのマスク着用など感染対策を」
マイコプラズマ肺炎、8年ぶり流行…専門家「人混みでのマスク着用など感染対策を」(医療ニュース)
主に子どもがかかるマイコプラズマ肺炎が8年ぶりに流行している。国立感染症研究所の8日の発表によると、9月29日までの1週間に全国約500の医療機関から報告があった患者数は、1医療機関あたり1・64人(速報値)となった。現在の調査方法となった1999年以来、過去最多だった2016年10月17~23日の患者数に並んだ。
都道府県別では、福井が最も多い5・33人で、埼玉の4・25人、岐阜の3・4人、東京の2・96人が続いた。
マイコプラズマ肺炎は、発熱や全身のだるさなどが表れ、熱が下がった後も3~4週間せきが続く。多くは軽症だが、一部は重症化したり、心筋炎などの合併症を引き起こしたりすることがある。患者の8割を14歳以下が占め、治療には抗菌薬が使われる。
東京医科大の岩田敏兼任教授(微生物学)は「秋から冬にかけて感染が広がりやすく、手洗いや人混みでのマスク着用などの感染対策をとってほしい。せきがひどくなったり、発熱が続いたりする場合は、早めの受診を」と呼び掛けている。[全文を読む] -
2024/10/09
「アレグラ」「ガスター」などジェネリックが普及した1100品目の先発薬、処方を希望なら自己負担増…今月から新制度
「アレグラ」「ガスター」などジェネリックが普及した1100品目の先発薬、処方を希望なら自己負担増…今月から新制度(医療ニュース)
ジェネリック医薬品(後発薬)がある特許切れの先発薬の処方を患者が希望した場合の自己負担額が今月、引き上げられた。厚生労働省が導入した新制度で、安価な後発薬の使用を促し、医療費を抑制する狙い。
この制度では、後発薬の発売から5年以上たった先発薬か、後発薬の使用割合が50%以上の先発薬が対象。抗アレルギー薬「アレグラ」や胃腸薬「ガスター」など約1100品目が該当する。後発薬との価格差の25%が公的医療保険の適用外となり、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額に上乗せされる。自治体から小児医療費の助成を受けている患者も、保険適用外分の支払いが生じるようになった。
例えば、自己負担3割の患者が、抗菌薬「ジスロマック錠250ミリ・グラム」を3日間服用する場合は支払額が288円から351円に上がる。一方、後発薬「アジスロマイシン錠250ミリ・グラム」を選べば、162円で済む。医師が、飲み合わせなどの医療上の理由から先発品が必要と判断したり、薬局に後発薬の在庫がなかったりした場合は、新制度は適用されず、負担額は増えない。
対象となる先発薬の一覧は、厚労省のウェブサイト
( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html )に掲載されている。[全文を読む] -
2024/10/08
異種移植「日本でこそ必要」…米で「ブタの腎臓」執刀の河合達郎教授
異種移植「日本でこそ必要」…米で「ブタの腎臓」執刀の河合達郎教授(医療ニュース)
米国で今年3月、ブタの腎臓を人間の生きた患者に移植する手術を執刀した河合達郎・米ハーバード大教授(外科学)が、川崎市で読売新聞などの共同インタビューに応じた。河合教授は、動物の臓器を人間に移植する異種移植について、臓器提供者が不足する日本でこそ、実用化の議論を進める必要性を訴えた。主な一問一答は次の通り。
――手術結果への所感は。
移植したブタの腎臓は正常に働き、手術直後から尿を作り、特別な拒絶反応もなかった。移植は成功したと考える。ただ患者の心臓が想定以上に悪く、2か月弱で死亡した。なるべく他に疾患のない透析患者に実施することが望ましかった。
――米国社会の反応は。
批判の声は、あまり聞かなかった。私たちも当初はためらいがあったが、患者団体の集会で患者から泣きながら「異種移植を進めてほしい」と懇願され、初めて「やらねば」と思った。手術後、患者団体から励ましの声が寄せられた。
米国では、他に疾患のない透析患者だと4、5年待てば人間の腎移植ができるが、それでも関心は高い。日本は米国に比べ、臓器移植を受けられる機会が圧倒的に少ない。日本でこそ異種移植は必要で、数年以内に手術ができるよう議論を進めてほしい。
――医療コストと感染症の心配は。
異種移植は最初に遺伝子改変ブタの開発費がかかるが、手術後にかかる医療費は患者1人あたり年間100万円以下だ。透析を続けるよりQOL(生活の質)も良い。
サルで長年、移植の実験をして、未知のウイルス感染はない。今回の手術後も考えられる限りの検査を続けたが、異常はなかった。それでも異種移植を始めて何十年かは、慎重に感染症を調べる必要がある。
――今後も異種移植手術を続けるのか。
もちろんだ。ただ米食品医薬品局(FDA)は、他に方法がない治療としてしか認めていない。日本のように待機期間が長い国の患者を、米国で移植するアイデアを検討している。医療レベルが高く、術後のケアができる移植外科医や内科医がいる国が条件だ。
私が研修医の頃は人間の臓器で[全文を読む]
最近更新された注目のコンテンツ2024/04/20 更新 | 新着情報一覧
- 2024/04/20【中国よもやま話】30回「なぜ犯罪組織が人気?~中国起源の任侠道が果たした社会的役割」
- 2024/04/15【医療コラム|石井正教授】第12回「フィジシャン・サイエンティストに」
- 2024/04/15【ゴルフコラム】第82回「「破竹」のナップが願うこと」
- 2024/04/10【医療コラム|中川泰一先生】第79回「マクロバイオームの精神的影響について」
- 2024/04/05【中国よもやま話】29回「21世紀版のグレート・ゲーム~ウイグルをめぐる情報戦」
- 2024/03/20【中国よもやま話】28回「現代の屯田兵~新疆生産建設兵団」
国試対策や進路など、医学生にオススメのコンテンツ
医師としてのキャリアを歩き出した研修医にオススメのコンテンツ
専門医取得を目指すドクターにオススメのコンテンツ
おすすめコンテンツ
成功を掴んだドクターの波瀾万丈の半生を描く
手技動画 人気TOP5
よく見られている手技動画をピックアップ!
研修医の味方!特集
英語で学ぶ!特集
情報収集しながら英語耳を鍛える
医学生のための厳選講演動画
「eレジフェア」講演動画を厳選して公開!
eレジフェアなら各病院とじっくり話せる!病院見学につながる!
レジデントインタビュー(毎月更新)
ログイン・新規登録
ドクゲ編集部より
- 【ドクター対談】基礎研究の経験を臨床に活かしているDr.古閑比佐志&Dr.佐々木治一郎のお二人による対談を配信開始!
- 【マンガ】諏訪中央病院 Dr.山中克郎(総合内科)の半生を描いたマンガが連載開始!毎月1日掲載!
- 【マンガ】八戸市立市民病院 Dr.今 明秀(救急)の半生を描いたマンガを連載中!毎月25日掲載!
- 2016年4月に発生した、熊本県・大分県を震源とする地震により、被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
- 【会員の皆さんへ】
事務局からのメールが届かないケースが増えています。マイページの登録情報を再度ご確認ください。