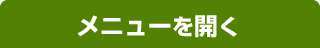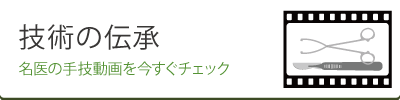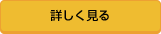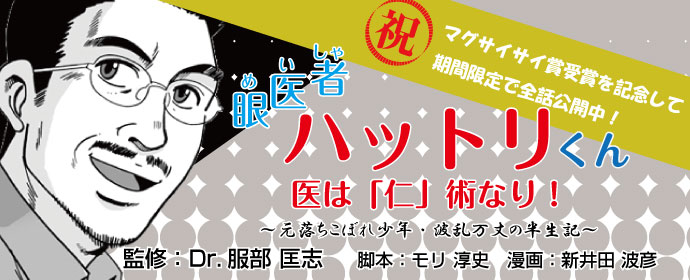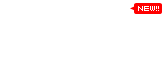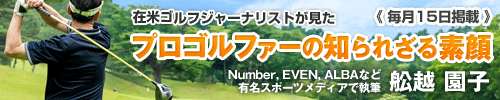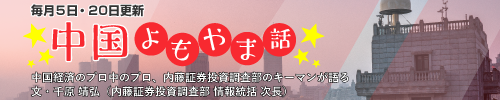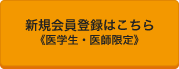おすすめコンテンツ
おすすめコンテンツ
成功を掴んだドクターの波瀾万丈の半生を描く
手技動画 人気TOP5
よく見られている手技動画をピックアップ!
研修医の味方!特集
英語で学ぶ!特集
情報収集しながら英語耳を鍛える
医学生のための厳選講演動画
「eレジフェア」講演動画を厳選して公開!
eレジフェアなら各病院とじっくり話せる!病院見学につながる!
レジデントインタビュー(毎月更新)
ログイン・新規登録
ドクゲ編集部より
- 【ドクター対談】基礎研究の経験を臨床に活かしているDr.古閑比佐志&Dr.佐々木治一郎のお二人による対談を配信開始!
- 【マンガ】諏訪中央病院 Dr.山中克郎(総合内科)の半生を描いたマンガが連載開始!毎月1日掲載!
- 【マンガ】八戸市立市民病院 Dr.今 明秀(救急)の半生を描いたマンガを連載中!毎月25日掲載!
- 2016年4月に発生した、熊本県・大分県を震源とする地震により、被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
- 【会員の皆さんへ】
事務局からのメールが届かないケースが増えています。マイページの登録情報を再度ご確認ください。