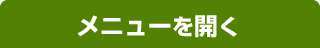-
慶応大の研究チームが、肝臓が持つ主要な機能を備えた細胞の塊「肝細胞オルガノイド」の作製に成功したと発表した。本物の肝臓に近いミニ臓器として創薬の研究などに役立つ成果で、科学誌ネイチャーに17日、掲載される。
肝臓は栄養素をためたり有害物質を分解したりする多彩な機能があるが、機能を完全に保ったまま肝細胞を増やし、肝機能を再現することは難しかった。
佐藤俊朗・慶応大教授(幹細胞医学)らのチームは、従来の細胞培養法に特定のたんぱく質を加えることで一つの肝細胞を100万倍以上に増やし、100日以上安定的に培養することに成功した。特定の成長ホルモンを投与すると肝臓に似た構造もでき、尿素やブドウ糖を作ったり解毒したりする機能も確認した。
東京科学大の油井史郎准教授(消化器再生学)の話 「肝不全治療に肝細胞オルガノイドを使う再生医療の足がかりにもなる成果だ」
-
【ジュネーブ=船越翔】世界保健機関(WHO)の加盟国は16日、感染症対策の新たな国際ルールとなる「パンデミック条約」の内容に合意した。WHOは5月の総会で条約の採択を目指す。ただ、条約が今後発効しても米国のトランプ政権は参加しない見通しで、ワクチン開発などで世界をリードする米国の不在を懸念する声が出ている。
ジュネーブで15日から翌16日未明まで夜通し続いた会合で、不参加だった米国を除く加盟国が条約の内容に合意した。WHOのテドロス・アダノム事務局長は「世界をより安全にするための合意を成立させた。歴史的な偉業だ」と強調した。
条約は、2022年から3年にわたりWHO加盟国が協議を続けてきた。背景には、国際連携やワクチンの分配などで各国の足並みがそろわず、世界の累計感染者数が7億7000万人超に上った新型コロナウイルスの流行の教訓がある。
読売新聞が入手した条文案によると、条約は「疾病の世界的流行は、生命や社会、経済に深刻な影響を及ぼす」とし、感染症対策の研究強化や途上国への技術移転などを盛り込んだ。
最大の焦点となったのは、医薬品の分配だ。条約では製薬企業が病原体の遺伝情報などを迅速に入手する見返りに、医薬品の生産量の一部をWHOに提供する仕組みを導入するとした。
医薬品提供の割合を巡って先進国と途上国の間で意見が対立する場面もあったが、企業が生産量の1割を無償提供し、さらに追加で1割を安価で提供することを目指す内容で決着した。
一方、WHOや専門家が注視するのが米国の動向だ。
トランプ米大統領は1月の就任直後にWHO脱退を表明し、米国は条約策定に向けた協議からも離脱。ワクチン懐疑論者として知られるロバート・ケネディ・ジュニア氏を厚生長官に充てるなど科学軽視の姿勢が目立つ。
新型コロナ禍では、米製薬企業のワクチン開発が先行し、日本を含む多くの国で利用された。米国が条約に参加せず、米企業からの医薬品提供もない場合、条約の実効性が著しく損なわれかねない。米国が条約に参加しなくても、米企業は医薬品提供に関与できるかどうかなど、詳細な制度設計は今後の課題となる。
-
京都大病院は14日、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を使って重い1型糖尿病を治療する治験で、国内初となる1例目の手術を行ったと発表した。患者の経過は良好で、既に退院したという。
矢部大介教授(糖尿病・内分泌・栄養内科)らがこの日、京大病院で記者会見した。
1型糖尿病は10~15歳の発症が目立ち、患者は国内に推定10万~14万人。通常、毎日数回のインスリン注射が必要だ。重篤な患者が血糖値をうまくコントロールできなければ、低血糖になって意識を失い、死亡する危険性もある。
治験の対象は20~64歳の重篤な患者3人。健康な人のiPS細胞から、膵臓でインスリンを放出している膵島細胞を作って数センチ四方のシートに加工し、患者の下腹部に複数枚を移植する。術後は5年間経過を観察し、安全性や効果を検証する。
1例目の手術は2月、京大病院で40歳代女性に行われ、移植細胞からインスリンが出ていることが確認された。細胞が異常増殖するなどの安全性の問題は見られないという。
女性は退院後も、自己注射を続けている。京大病院は移植細胞の生着とインスリンの分泌状況を確認しながら、将来的に注射の投与量を減らしたいとしている。
移植する細胞数は2、3例目で段階的に増やす予定で、来年、3例の安全性に関する中間発表を行う。その後、シートを製造する京大発の新興企業が米国や欧州での国際共同治験を実施する計画という。矢部教授は今回の治療法について「2030年以降の実用化を目指したい」と話した。
◆ 1型糖尿病 =膵臓にある膵島細胞が自己の免疫細胞などに破壊され、血糖値を下げるインスリンがほとんど分泌されなくなる。患者は世界に推計800万人。糖尿病のうち1型は約5%で、生活習慣の影響が大きい2型とは異なる。
1型糖尿病は、毎日のインスリン注射に耐えながら暮らしている子どもの患者も多い。新たな治療法で注射が不要になれば命を脅かす低血糖を回避でき、患者のQOL(生活の質)も飛躍的に改善する。
将来的には中高年に多い2型糖尿病の重い患者も対象になりうる。予備軍を含めて2型の患者は国内に
-
うつ病や認知症のリスクを高める加齢性難聴の対策を進めるため、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会など8団体は、適切な医療支援を図る共同宣言をまとめた。聞こえにくさを感じる人の受診率を80%以上に引き上げ、低迷する補聴器の普及率の向上を目指すなど四つの目標を掲げ、健康寿命の延伸につなげたい考えだ。
加齢性難聴は、加齢に伴い音を感じる細胞が減り、耳が聞こえにくくなる病気。75歳以上の3割超が難聴を自覚している。治療法はないが、早期の受診で進行を遅らせ、補聴器の装着などで生活の質を維持できる。
日本補聴器工業会の2022年の調査では、聞こえにくさを自覚し、耳鼻科などを受診した人の割合は38%、相談を受けた医師が補聴器を勧めた割合も37%にとどまる。難聴を自覚する人のうち補聴器を使う割合は15%と、欧州各国の40~50%台より低迷している。
共同宣言には、高齢者や認知症の診療を専門とする学会も参加。加齢性難聴を放置すると、コミュニケーションが難しくなり、社会的な孤立や認知機能の低下につながると指摘し、対策として、〈1〉全ての世代を対象とした難聴の検査体制の整備〈2〉適切な診断や難聴の進行を抑制する生活指導の実施〈3〉補聴器の装着の推進――を挙げた。
これらを実現する目標として、受診率や医師による補聴器使用の提案、補聴器への満足度、補聴器の購入費用を補助する自治体の割合について、いずれも80%以上を目指すとした。
大森孝一・同学会理事長は、「宣言に参加する学会と連携して対策を進め、目標を達成したい」と話している。
-
膵臓の細胞が正常に働かない「1型糖尿病」の治療について、徳島大病院(徳島市)は、患者自身の脂肪からインスリンを出す細胞を作り、再生医療技術で患者に移植して根本的治療を目指す治験を今夏にも始めると発表した。安全な世界初の治療方法を目指す。(吉田誠一)
糖尿病のうち1型の割合は約5%で、膵臓内の細胞の塊「膵島」が壊れ、血糖値を制御できなくなる病気。若い頃から発症し、毎日何度もインスリン注射が必要となる。病院によると、根本的な治療方法では、脳死ドナーから膵島を取り出し、患者に移植する方法があるが、日本では患者10万人あたりのドナーは0・6人しかおらず、移植は困難となっている。
そこで消化器・移植外科の池本哲也医師(53)らは、患者からの採取や臨床への応用が安全で容易な脂肪由来の幹細胞に着目した。再生医療技術で、“膵島”(インスリン産生細胞・IPC)にして移植することにし、2018年度から研究を開始した。
1型患者の皮下脂肪から作った膵島をマウスに移植したところ、2週間後から血糖が正常化し、1年以上持続。豚でも腸間膜内に移植すると、同様の効果を確認できた。
池本医師らは、この「IPC自家移植」を臨床応用。局所麻酔した患者から皮下脂肪組織を1グラム採取し、分離・精製して脂肪由来幹細胞とし、4週間かけて培養しながら分化・成熟させ、IPCを作製する。体への負担が少ない腹腔鏡手術で患者の腸間膜内に注入して移植する方法を確立した。このうち培養技術については特許も取得した。
徳島大で3月24日にあった記者会見で、池本医師らは「この治療方法は血糖の制御に優れるうえ、患者の自家細胞を使うため拒絶反応がなく、毒性や移植で腫瘍を作ることもない」と利点を強調。「人への初めての投与で効果と安全性を示し、治療法を世界に発信したい」と話した。
1型の治療では、京都大病院がiPS細胞(人工多能性幹細胞)から作った細胞シートを移植する治験を実施する計画がある。池本医師は「患者自身の細胞を使うこちらの治療法は(遺伝子導入などがないため)DNAダメージの危険性が少なく、安全面でアドバンテージがある」と強調した。
-
激しいせきが続く百日せきの流行が拡大している。感染症を監視する国立健康危機管理研究機構によると、今年の累計患者数は3月30日時点で4771人(速報値)に達し、2024年1年間の4054人をすでに上回った。専門家は「重症化を予防するため、子どものワクチン接種を検討してほしい」と呼びかけている。
百日せきは、細菌によって引き起こされ、主にせきやくしゃみなどの飛沫でうつる。せきで呼吸困難になることがあり、生後6か月未満の乳児が重症になりやすく、肺炎や脳症などを引き起こすと命にかかわる。感染症法で、18年から全ての患者を把握することになった。
今年の患者数は1月6~12日に135人が確認されて、その後も増加傾向が続く。直近1週間の3月24~30日には578人と、18年以降で最多となり、都道府県別では新潟が73人、兵庫が36人、沖縄が35人となっている。治療には抗菌薬が使われるが、薬が効きにくい耐性菌が大阪や沖縄などで見つかり、国内で広がっている恐れがある。
百日せきを含む5種混合ワクチンは、公費による定期接種の対象で、生後2か月から2歳半頃までに4回の接種が標準的となっている。日本小児科学会は、乳児の早期接種と、小学校入学前と高学年での任意接種を促している。
浜松医科大の宮入烈教授(小児科学)は「コロナ禍では流行が抑えられ、免疫を持つ人が少なくなっている。ワクチンの効果が薄れる時期の追加接種も検討してほしい」と話している。
-
iPS細胞(人工多能性幹細胞)から心臓の筋肉(心筋)の細胞シートを作って心臓病の患者に移植する治療法について、大阪大発の新興企業「クオリプス」(東京)は8日、細胞シートの製造販売承認を厚生労働省に申請した。iPS細胞を使った医療用製品の承認申請は世界初とみられる。
対象となるのは、心筋梗塞などで心臓の動きが悪くなる「虚血性心筋症」の患者の治療。悪化すると心臓移植などが必要になるが、国内では臓器提供者が少ない現状がある。
同社の最高技術責任者を務める阪大の澤芳樹・特任教授らは、人のiPS細胞から心筋細胞を作り、直径3・5~4センチ、厚さ0・1ミリのシートを作製。2020年1月~23年3月、阪大病院など4施設で患者計8人に対し、1人あたりシート3枚(細胞数は計約1億個)を心臓に貼り付ける治験を行った。
澤特任教授や同社によると、移植を受けた8人全員で安全性を確認。移植後26週よりも52週の方が症状の改善がみられ、社会復帰も果たしているという。
同社の草薙尊之社長は「ようやく第一歩を踏み出すことができた。一日も早く承認をいただき、患者さんに治療を届けたい」と話している。同社が作製したiPS細胞由来の心筋細胞のシートは、13日開幕の大阪・関西万博で展示される。
iPS細胞を活用した医療用製品の開発は国内外で進み、製薬大手の住友ファーマなどが今年中にも、パーキンソン病の患者に移植するiPS細胞由来の神経細胞について承認申請を目指している。
八代嘉美・藤田医科大教授(幹細胞生物学)の話「既存の治療では改善が見込めない患者に対し、治療の選択肢が増えれば大きな意義がある。iPS細胞の技術を新たな医療として申請できる段階に来たのは画期的なことだ」
-
体調不良で救急を受診すべきかどうかを対話型AI(人工知能)サービス「チャットGPT」に答えさせた助言について、利用者が不正確に解釈する恐れがあるとの見解を日本救急医学会がまとめた。同学会は、判断に迷う際は医療関係者に相談し、分かりやすい言葉で解説してもらうことが必要だとしている。
同学会は昨年、症状から緊急度を判定する総務省消防庁の救急受診ガイドの事例を使い、チャットGPTに救急受診の必要性を尋ねた。得られた回答について、救急の専門医ら7人が評価し、医療関係者以外の157人にどう解釈したかをアンケートした。
その結果、胸の痛みが30分以上続くなど緊急度が高い314例のうち97%で合理的な理由を示した上で判断しており、回答は適切と専門家から評価された。一方、医療関係者以外の人が回答を見て「救急受診が必要」と解釈したのは43%だった。緊急度の低い152例では、回答の89%が専門家から適切とされたが、医療関係者以外の人で「救急受診が不要」と判断したのは32%だった。
調査を行った東京慈恵医科大の田上隆教授(救急災害医学)は「対話型AIの回答の精度は思ったより高かったが、利用者に正しく解釈されない恐れがある限り、過度な依存は避けるべきだ」と指摘している。
-
東京都墨田区の社会福祉法人「賛育会」は31日、運営する賛育会病院で、親が育てられない子どもを匿名で預ける「いのちのバスケット」(赤ちゃんポスト)と、妊婦が病院の担当者にのみ身元を明かして出産する「内密出産」の受け入れを始めたと発表した。国内の医療機関では熊本市の慈恵病院に続いて2例目。
同会によると、いのちのバスケットは生後4週間以内の子どもが対象で、病院1階に受け入れ専用の部屋を設けた。子どもが預けられた場合、病院は児童相談所(児相)と警察に連絡。児相が乳児院などにつなぐ。
東京都墨田区の社会福祉法人「賛育会」は31日、運営する賛育会病院で、親が育てられない子どもを匿名で預ける「いのちのバスケット」(赤ちゃんポスト)と、妊婦が病院の担当者にのみ身元を明かして出産する「内密出産」の受け入れを始めたと発表した。国内の医療機関では熊本市の慈恵病院に続いて2例目。
同会によると、いのちのバスケットは生後4週間以内の子どもが対象で、病院1階に受け入れ専用の部屋を設けた。子どもが預けられた場合、病院は児童相談所(児相)と警察に連絡。児相が乳児院などにつなぐ。区は戸籍を作成し、区長が命名する場合もある。
内密出産についても、国の指針に沿って行政と連携する。子どもは病院から連絡を受けた児相が保護。成長して出生の経緯などを知りたくなった場合に備え、病院は母親の身元情報などを保管する。出産費用は原則、母親側に負担を求めるが、相談に応じるとした。
31日に記者会見した賛育会病院の賀藤均院長は、「赤ちゃんの遺棄や虐待死などを回避するための緊急で最終的な手段」と述べた。
慈恵病院では2007年に赤ちゃんポストの運用を始め、24年3月末までに179人が預けられた。19年に導入を表明した内密出産では、21年12月からの3年間で約40人が生まれた。
-
病院を受診した患者の約4割は診察までに30分以上待たされる一方、診察時間は10分未満で終わるケースが7割近くに上ることが、厚生労働省が公表した2023年の受療行動調査で明らかになった。
調査によると、外来で訪れた病院での待ち時間について、「30分以上」と答えた患者は43%に上っており、大規模な病院ほど割合が高い傾向にあった。診療などの満足度を尋ねると、待ち時間について26%が「不満」を感じていた。
一方、外来での診察時間を「10分未満」とした患者は69%だった。ただ、診察時間について「不満」と回答したのは7%にとどまっていた。
病気別では、循環器や呼吸器の病気で診察時間が短く、「10分未満」が7割を超えた。消化器や精神の病気での診察時間が長くなる傾向があり、「30分以上」との回答が、消化器疾患の9%、精神疾患の7%を占めた。
受療行動調査は、医療機関を利用した患者に状況などを聞き取るもので、厚労省が3年ごとに実施している。今回の調査は23年10月17~19日、全国の488病院を訪れた患者に調査票を配布し、10万3630人分の有効回答を得た。