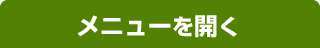-
環境省は25日、発がん性が指摘される化学物質「PFAS」の一種「PFOS」と「PFOA」について、全国の河川や地下水の含有量を調査した結果、2023年度は22都府県の242地点で国の暫定目標値(1リットル当たり50ナノ・グラム)を超えたと明らかにした。同日開催された同省の有識者会議で報告された。
今回の調査は、39都道府県の2078地点で行われた。前年度調査は38都道府県の1258地点で行われ、16都府県の111地点で目標値を超過していた。調査地点、超過地点ともに大幅に増加した。同省は超過地点のあった自治体に対し、井戸水や河川の水を飲用に使わないよう注意を呼びかけている。
最大値は大阪府摂津市の地下水で、1リットル当たり2万6000ナノ・グラムだった。府によると、近くの化学製品の製造工場で以前、PFOAを使用したことがあり、工場が汚染源の一つとみられるという。付近住民の飲用には使われてはいないという。
-
国立がん研究センターは肺がん検診のガイドライン(指針)を改訂した。たばこをたくさん吸ってきた50~74歳に年1回、放射線の被曝量を抑えた低線量CT(コンピューター断層撮影)検査を受けることを新たに勧めた。がんの早期発見で死亡リスクを減らす効果が確認できたためとしている。厚生労働省は市町村が行うがん検診の指針に反映するかを検討する。
CT検査の対象は、50~74歳のうち、1日に吸うたばこの平均本数に喫煙年数をかけた値が600以上となる「重喫煙者」となる。禁煙してから15年以内の人も含まれる。2006年度にまとめた従来の指針では年1回、胸部エックス線検査と痰を調べる検査の併用が推奨されていた。
指針を見直した専門家らのチームは、重喫煙者への低線量CT検査は、胸部エックス線検査と比べ、肺がんによる死亡リスクを16%下げるとする米国の研究など複数のデータを踏まえた。
一方、検査の被曝によりがんになるリスクは高まらないと判断した。
-
未知の感染症の流行を把握するため、今年度から国の患者数調査の対象に加わった「急性呼吸器感染症(ARI)」について、国立健康危機管理研究機構は22日、初の調査結果を発表した。せきやのどの痛みといった風邪の症状を示す呼吸器感染症の総称で、13日までの1週間に報告された患者数は、1医療機関あたり49・38人だった。国は今後のデータの推移を注視していく方針だ。
ARIは、感染症法上の「5類」に位置づけられ、全国約3000の定点医療機関から1週間分の患者数の報告を受ける定点把握対象として7日から集計が始まった。個別に患者数が報告されるインフルエンザや新型コロナウイルスなども含まれる。
これまでは、風邪症状があっても、診断がつかなかった場合は報告の対象外で、この中に新たな感染症が含まれていても、見逃してしまう恐れがあった。
調査では、定点医療機関のうち、300の医療機関から患者の鼻ぬぐい液など検体の提出を受け、ウイルスなどの病原体が含まれていないかも調べる。
谷口清州・国立病院機構三重病院名誉院長(感染症疫学)は、「ARIの調査で、インフルエンザや新型コロナなど既知の感染症が、どれぐらいの割合で流行しているのかが分かる。これらの流行状況を継続して把握することで、未知の感染症が発生した際、早期に察知し、対処することが可能になる」と指摘している。
-
厚生労働省の専門家部会は21日、米モデルナが開発したRSウイルスワクチンについて、製造販売の承認を了承した。遺伝物質「メッセンジャーRNA(mRNA)」を使ったタイプで、正式に承認されれば、新型コロナウイルス以外の感染症で採用される初のmRNAワクチンとなる。
RSウイルスは、風邪のような症状が表れ、免疫力が弱い高齢者や乳児の場合は重い肺炎を起こすことがある。このワクチンは、米国や欧州で承認されており、60歳以上が接種対象となる。
-
感染力が強い麻疹(はしか)の患者の増加が続いていることから、国立健康危機管理研究機構(JIHS)は、感染拡大に注意を呼びかける文書を15日付で発表した。
麻疹はウイルス感染により、発熱や発疹などの症状が表れる。脳炎や肺炎を起こし死亡することもある。
同機構によると、今年に入って今月6日までの累計感染者数は66人(速報値)で、昨年1年間の45人を上回る。このうち半数以上の37人は流行している海外で感染したとみられる。国別では、ベトナムが29人を占め、タイは3人、フィリピンは2人。都道府県別の感染者数は、大阪が10人、神奈川と兵庫は8人、東京が7人などとなっている。
文書では、開催中の大阪・関西万博に国内外から多くの人が集まるため、感染拡大の恐れがあると指摘。訪日外国人と接する機会が多い人や、流行している国や地域へ渡航を予定している人は、ワクチンの接種歴を確認するよう求めている。
-
救急車を呼ぶかどうか迷った時に相談できる電話窓口「#7119」が大型連休中、つながりにくくなるケースがある。不要不急の119番の件数を抑えるために導入されたが、認知度が上がったことで電話が集中し、対応が追いつかないという。自治体などはゴールデンウィーク(GW)に向け、つながりにくい場合は携帯電話アプリなど類似サービスの利用検討を呼びかけている。(飯田拓)
「いつから、どのような症状ですか」。大阪市消防局にある「救急安心センターおおさか」(大阪市西区)で今月上旬、窓口を担当する8人の看護師らがパソコン画面を見ながら、電話の相手に尋ねていた。
専用のプログラムに沿って症状を聞き取り、「緊急度」を判定。必要ならその場で消防に電話を転送する。判断に迷った場合、常駐の医師に相談する。
同市は2009年に制度を導入。10年12月以降は大阪府内全域からの相談を受け付けている。24年の対応件数は約34万7700件で、11年から10万件以上増えた。現在は回線を当初の4倍の16本に増やし、曜日や時間帯によって2~16人の看護師を配置している。
それでも、開いている医療機関が少ない年末年始やGWの大型連休中は電話が殺到し、対応しきれない場合がある。平日や通常の土日は1日600~1500件ほどだが、インフルエンザが流行した昨年12月29日は1日で約2800件と、過去最多を記録した。「約30秒に1件」の計算で、順番待ちの時間が長くなったという。勤務歴10年の看護師庄司京子さん(64)は「相談が終わった瞬間に次の電話を取るような状況がずっと続いていた」と振り返る。
総務省消防庁によると、高いニーズに対応するため、大型連休中は態勢を強化する必要がある。ただし、単に回線を増やしても、連休中だけ勤務できる人材を見つけるのは難しい。導入して間もない自治体では、不慣れなため相談の多い時期や時間帯を予想しきれないこともあるという。
同庁が昨年7月に公表した、「#7119」を運用する30地域(当時)への調査結果によると、着信に対応できた割合を示す「応答率」は、回答した19地域の約半数が8割台だった。大阪府は72・4%で、最高は神戸市の97・3%。全県での運用が初年
-
医師が治療しながら負傷者を搬送できるドクターヘリを大規模災害時に効率的に活用するため、厚生労働省が運用指針を初めて改定した。都道府県の災害対策本部に離着陸場所などの調整を一元化し、ヘリを運航する病院側が治療や搬送に専念できるようにした。都道府県をまたぐ広域災害時には、厚労省に連絡窓口を設け、ヘリの需要などの情報を集約することも盛り込んだ。
新たな指針は各都道府県に3月31日付で通知された。昨年の能登半島地震では離着陸場所が決まらず時間を要したこともあり、現場での混乱をなくす狙いだ。
改定では、同本部が離着陸場所や給油場所などの調整にあたる。消防や自衛隊など各機関のヘリがどの現場に向かうのかについても、やりとりを一手に引き受ける。結果を受け、病院側が優先順位の高い場所などを判断し、運航する。
能登半島地震では、各地から派遣されたドクターヘリの離着陸場所の確保が難航した。各機関との情報共有が不十分で複数のヘリが同じ現場に向かう混乱もあった。石川県災害対策本部と、その指揮下でヘリを運航する病院側の双方に、けが人などに関する連絡や問い合わせが相次ぎ、情報が錯綜したことも要因とみられる。
都道府県をまたぐ広域災害時には、被災した都道府県と関係省庁などとの連絡窓口「ドクターヘリ支援本部」を厚労省内に設置することも盛り込んだ。被災地以外から派遣できるヘリの数や被災地の要望、情報を病院側にスムーズに伝える考えだ。厚労省地域医療計画課は「指揮系統を見直し、現場が混乱せず、ヘリを円滑に運航できるよう関係機関に周知していく」と話している。
◆ドクターヘリ= 都道府県が導入し、救命救急機能を持つ病院に配備している。厚労省によると、東日本大震災時に全国で26機あり、現在は57機。能登半島地震では8機が出動し、計84人を搬送した。
-
人のiPS細胞(人工多能性幹細胞)から作った神経細胞をパーキンソン病の患者7人の脳に移植した治験結果を、京都大病院が発表した。このうち6人で治療効果を調べたところ4人で症状の改善がみられ、介助がいらなくなった人もいた。年度内にも製薬大手が国に細胞製品の製造販売について承認申請する見通しだ。論文が17日、科学誌ネイチャーに掲載される。
パーキンソン病は、脳内で運動の調節に関わる物質ドーパミンを作る神経細胞が減少して発症する難病で、手が震えたり歩行が困難になったりする。国内患者数は推計29万人、世界では1000万人を超える。50歳以上で発症することが多く、65歳以上では100人に1人程度が患っているとされる。根本的な治療法はなく、ドーパミンの分泌を促す薬で症状は抑えられるが、進行を止めるのは難しい。
今回の治験の対象患者は転倒しやすいなどの症状があり、薬が十分に効かない50~69歳の男女7人。
京大iPS細胞研究所長の高橋淳教授(脳神経外科)らは2018~21年、健康な人のiPS細胞から作った神経細胞を特殊な注射針を使って脳に500万~1000万個ずつ移植し、それぞれ2年間の経過観察を行った。その結果、7人全員で、移植した細胞にがん化などの異常はみられず、安全性を確認できた。
安全性のみを確認した1人を除く6人で有効性の評価も行われ、いずれも移植した細胞が働き、ドーパミンを出していることがわかった。このうち4人では、症状や運動機能の改善がみられ、介助が不要になったり、一定期間車いすを使わずに生活できるようになったりする人もいた。
残る2人のうち1人はこの治療だけでは効果が見られなかったが、薬の併用で改善した。別の1人は薬を併用しても改善しなかった。
今回の治験で神経細胞の製造を担った製薬大手・住友ファーマなどは実用化を目指し、年度内にも厚生労働省に承認申請を行う方針。認められれば公的医療保険が適用される。
高橋所長は「良くなった患者さんがいたことは率直にうれしい。一日も早く多くの人に治療を届けたい」と話している。
赤松和土・順天堂大教授(再生医学)の話「安全性を確認
-
慶応大の研究チームが、肝臓が持つ主要な機能を備えた細胞の塊「肝細胞オルガノイド」の作製に成功したと発表した。本物の肝臓に近いミニ臓器として創薬の研究などに役立つ成果で、科学誌ネイチャーに17日、掲載される。
肝臓は栄養素をためたり有害物質を分解したりする多彩な機能があるが、機能を完全に保ったまま肝細胞を増やし、肝機能を再現することは難しかった。
佐藤俊朗・慶応大教授(幹細胞医学)らのチームは、従来の細胞培養法に特定のたんぱく質を加えることで一つの肝細胞を100万倍以上に増やし、100日以上安定的に培養することに成功した。特定の成長ホルモンを投与すると肝臓に似た構造もでき、尿素やブドウ糖を作ったり解毒したりする機能も確認した。
東京科学大の油井史郎准教授(消化器再生学)の話 「肝不全治療に肝細胞オルガノイドを使う再生医療の足がかりにもなる成果だ」
-
【ジュネーブ=船越翔】世界保健機関(WHO)の加盟国は16日、感染症対策の新たな国際ルールとなる「パンデミック条約」の内容に合意した。WHOは5月の総会で条約の採択を目指す。ただ、条約が今後発効しても米国のトランプ政権は参加しない見通しで、ワクチン開発などで世界をリードする米国の不在を懸念する声が出ている。
ジュネーブで15日から翌16日未明まで夜通し続いた会合で、不参加だった米国を除く加盟国が条約の内容に合意した。WHOのテドロス・アダノム事務局長は「世界をより安全にするための合意を成立させた。歴史的な偉業だ」と強調した。
条約は、2022年から3年にわたりWHO加盟国が協議を続けてきた。背景には、国際連携やワクチンの分配などで各国の足並みがそろわず、世界の累計感染者数が7億7000万人超に上った新型コロナウイルスの流行の教訓がある。
読売新聞が入手した条文案によると、条約は「疾病の世界的流行は、生命や社会、経済に深刻な影響を及ぼす」とし、感染症対策の研究強化や途上国への技術移転などを盛り込んだ。
最大の焦点となったのは、医薬品の分配だ。条約では製薬企業が病原体の遺伝情報などを迅速に入手する見返りに、医薬品の生産量の一部をWHOに提供する仕組みを導入するとした。
医薬品提供の割合を巡って先進国と途上国の間で意見が対立する場面もあったが、企業が生産量の1割を無償提供し、さらに追加で1割を安価で提供することを目指す内容で決着した。
一方、WHOや専門家が注視するのが米国の動向だ。
トランプ米大統領は1月の就任直後にWHO脱退を表明し、米国は条約策定に向けた協議からも離脱。ワクチン懐疑論者として知られるロバート・ケネディ・ジュニア氏を厚生長官に充てるなど科学軽視の姿勢が目立つ。
新型コロナ禍では、米製薬企業のワクチン開発が先行し、日本を含む多くの国で利用された。米国が条約に参加せず、米企業からの医薬品提供もない場合、条約の実効性が著しく損なわれかねない。米国が条約に参加しなくても、米企業は医薬品提供に関与できるかどうかなど、詳細な制度設計は今後の課題となる。