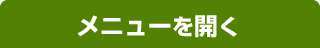-
口の中の粘膜を調べるだけで、食道がんの有無を高精度に判別する方法を京都大などのチームが開発した。今後、将来の発症リスクも予測できるようにし、体への負担が少なく、がんの早期発見や予防にもつながる検査キットとして実用化を目指す。論文が国際科学誌に掲載された。
食道がんは国内で年間約2万4000人が新たにかかり、約1万人が亡くなっている。飲酒や喫煙などの生活習慣や加齢によって遺伝子が変異した細胞が増加し、正常な細胞に交じる「体細胞モザイク」が原因とされる。
チームは、特に東アジアでは食道がんの大半を占める「 扁平へんぺい 上皮がん」の患部と、頬の粘膜が同様の細胞でできていることに着目。食道がん患者121人と患者ではない101人の頬の粘膜を綿棒で採取し、遺伝子を解析した。
結果、患者の粘膜からはより多くの遺伝子変異が見つかり、飲酒量に応じて変異の数も増える傾向を確認。その上でがんの増殖などにかかわる遺伝子変異の蓄積数を調べることで、約8割の精度で食道がんかどうかを見分けることができた。患者以外の人を今後、追跡調査し、将来の発症リスクの算出も目指す。
チームの垣内伸之・京大特定准教授は「将来の発症確率をつかめれば、健診段階で詳しい検査の実施や生活習慣の改善を助言しやすくなる利点がある」と話す。
吉田健一・国立がん研究センター研究所がん進展研究分野長の話 「細胞の高感度な解析によって確立できた有効な検査法。粘膜採取を誰でも画一的に行えるかを検証することも必要だ」
-
厚生労働省はAI(人工知能)などデジタル技術を活用した「プログラム医療機器(SaMD)」開発を目指す新興企業への支援を強化する。全国の大学や病院に拠点を設け、専門知識を持つ人材の育成や機器の有用性の実証を開始、海外展開も視野に入れた革新的な機器の創出につなげる。
SaMDは、のどの画像を撮影することで痛みを伴う検査をせずにインフルエンザ感染を判定したり、内視鏡画像からがんが疑われる病変を検出して見逃しを減らしたりするプログラムなどをいう。一般の医療機器と同様に国の承認を受ける。患者や医師の負担軽減に役立つことが期待され、高齢化が進む先進諸国で働き手が減る中、成長産業に位置付けられる。
厚労省は昨年度、日本医療研究開発機構を通じ、医療機器産業の振興拠点の整備を始めた。今年度は6月にも15か所程度の拠点を選定、このうち数か所が、SaMDの実用化を支援する拠点となる見通しだ。
拠点は、1か所あたり年間で最大1億1000万円の補助を受ける。開発経験が豊富な職員を配置、企業から受け入れた研究者らを専門人材として育成するほか、SaMDの安全性や有効性を確かめる臨床試験を実施できる体制も整える。
企業からの相談も受ける。製品の課題や評価方法を助言し、国内外で医療機器の承認を受け、海外展開の戦略策定を支援する。
実用化のノウハウを持つ大手企業や、資金の調達先となるベンチャーキャピタルとの橋渡しも担う。
海外では、新興企業発の医療機器を大手企業が育成、買収して市場に投入される例が多い。一方、国内ではこうした動きは鈍く、新興企業にとって、資金調達や承認を得るまでの煩雑な手続きが、実用化を阻む「死の谷」となっている。関連の法規制を熟知し販路を持つ大手企業とのつながりが弱く、医療分野に精通したベンチャーキャピタルが限られることが背景にある。
-
政府は今年度、マイナンバーカードと保険証を一体化させた「マイナ保険証」を活用し、救急隊員が患者の医療情報を確認する仕組みを全国で導入する。10月末までに全ての消防本部で展開し、適切な応急処置や搬送する病院の選定につなげ、救える命を増やしたい考えだ。
救急隊員が現場に到着した際、急病人らの同意を得て専用のカードリーダーでマイナ保険証を読み取ることで、病歴や通院歴のある医療機関、服用している薬などを確認できるようになる。搬送先の病院ともこれらの情報を共有し、受け入れ準備を進めてもらうことも可能だ。
総務省消防庁がカードリーダーなど、機材の整備費用を負担して利用を促して準備が整った各消防本部から順次実施し、最終的には全720消防本部の5334隊で導入する。
消防庁は昨年度、先行事例として、東京消防庁や大阪市消防局など、67消防本部の計660救急隊で実証事業を行った。約2か月の期間中、搬送時にマイナ保険証の情報を閲覧したケースは1万1398件あったという。
なかには現場に駆けつけたところ、90代の男性が意思疎通できない状態にあり、一緒にいた妻も既往歴を把握していなかったが、マイナ保険証から服用薬やかかりつけ病院が分かった事例があった。また、意識がもうろうとしていた患者の服薬情報から病名を推測し、搬送先の医療機関が検査や手術の準備に取りかかることができたなど、有効性が証明された。
-
がん治療が「AYA世代」と呼ばれる若い患者の卵巣機能に与える影響を見極めようと、大阪急性期・総合医療センター(大阪市)などのチームが新たな研究に乗り出した。不妊になるリスクが検討されていない薬が増えていることなどから、対応する指針を作成し、患者が最適な治療を選べる医療の確立を目指す。
国の統計などによると、国内では年間約2万人のAYA世代が新たにがんと診断されているとみられる。手術や放射線照射、抗がん剤などで妊娠しにくくなる恐れがあるため、妊娠の選択肢を残したい患者は、治療開始前に受精卵や卵子、卵巣組織を凍結保存する温存療法の検討を迫られる。
日本 癌がん 治療学会は、将来の妊娠を見据えたがん治療に関する指針を示しているが、米国の学会の指針に準拠しており、日本人女性での影響は十分に検証されていない。近年は指針に載っていない新薬も増えた。
今回の研究では、AYA世代を中心とするがん患者約500人を対象に、治療前と治療1年後、2年後の血液を採取。特定のホルモンの値などから、それぞれの治療で卵巣機能がどう変化したかを調べる。
AI(人工知能)を活用し、治療が妊娠に及ぼす影響を予測するモデルを開発し、リスクを最小限に抑える治療法を提案することをめざす。研究には埼玉医大、聖マリアンナ医大なども参加する。
研究代表を務める同センターの森重健一郎・生殖医療センター長は「新たな命を授かりたいという患者さんの希望を実現する医療が必要」と話す。チームは16日まで、検査費用など必要な資金を募るクラウドファンディングを実施。9日に第1目標の650万円に達したため、目標額を800万円に引き上げ、支援を呼びかけている。
◆ AYA世代 =「思春期・若年成人」を意味する英語(Adolescent and Young Adult)の頭文字で、15~39歳でがん治療を受けた患者を指すことが多い。がん治療に加え、将来の妊娠に備えた温存療法を受けるかの決断も迫られ、心身、経済的な負担が大きい。
-
新型コロナウイルスの感染症法上の扱いが2023年5月に季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行してから8日で2年となる。多くの人が日常を取り戻す中、後遺症を患い、倦怠感などから学校に通えない子どもたちがいる。周囲の理解も得にくく、保護者らは行政に支援の拡充を求めている。(浜田喜将)
「多くの病院で『思春期特有の問題』と片付けられ、たくさん傷ついた」。さいたま市の中学3年の女子生徒(14)はこぼした。
小学6年のとき、コロナに感染した。高熱などの症状は1週間で治まったが、約2か月後、腹痛や頭痛、倦怠感に襲われた。学校を休みがちになり、複数の病院で精密検査を受けたものの、診断結果は「異常なし」。東京の病院でコロナ後遺症だとわかったのは、感染から1年後だった。
元々、テニスに打ち込み、運動が大好きだった。中学進学後は症状が悪化し、中1の6月から登校できなくなった。現在はほぼ寝たきりで、オンライン授業の受講も難しいという。自宅で週3回、はり治療を受けており、高額な治療費がかかる。母親(48)は「国や自治体に支援してほしい」と訴える。
大阪市の私立中学3年の男子生徒(15)も小6で後遺症を発症し、中学入学後に通学できなくなった。
学校にオンライン授業を求めたところ、「学校の方針」との理由で断られた。交渉の末、授業の映像視聴がようやく認められたが、同級生と交流できず、強い孤独を感じたという。
新型コロナ後遺症について、世界保健機関(WHO)は「感染から3か月時点で別の病気では説明できない症状があり、それが2か月以上続く」と定義している。
厚生労働省によると、国内患者数のデータはないが、WHOの研究では、コロナ感染者の約6%が後遺症を発症するとされる。国内のコロナ感染者は、5類に移行した23年5月時点で累計約3380万人に達しており、相当数が後遺症を患った可能性がある。
岡山大病院の大塚文男教授によると、21年2月から25年3月末までに診察した後遺症患者は1125人に上った。うち14%(157人)が10歳代で、症状別では倦怠感が最も多く、頭痛、睡眠障害と続いた。味覚や嗅覚
-
激しいせきが続く百日せきについて、国立健康危機管理研究機構(JIHS)は7日、今年の累計患者数が1万人を超えたと発表した。4月21~27日の1週間の患者数は2176人(速報値)で、前週の1884人を上回り、5週連続で過去最多を更新した。
今年の累計患者数は1万1921人に上る。昨年1年間(4054人)の約3倍で、治療薬が効きにくい耐性菌の広がりが指摘されている。
百日せきは、細菌によって引き起こされ、主にせきやくしゃみなどの飛沫でうつる。特に乳児は重症になりやすく、呼吸困難や肺炎などを起こすと命に関わる。JIHSなどは、ワクチン接種が可能になる生後2か月以降の速やかな接種を呼びかけている。
-
がん検診の実効性を高めようと、厚生労働省は、公費を使った住民検診に加えて職場や人間ドックでの受診状況についても、市町村が一括して把握する仕組みを整備する方針を決めた。いずれの検診も受けていない人や、精密検査が必要との結果を放置している人を確実に見つけて受診を勧奨し、がんの早期発見と治療につなげる。
厚労省は、先月23日の有識者検討会で方針を提案し、了承された。市町村が住民検診の案内を個別に通知する際に受診状況の調査も依頼、検査日や結果などをインターネットで申告してもらう方法を想定していることも報告した。今後、把握の方法や導入時期を検討会で議論する。
市町村は現在、厚労省の推奨に基づき、胃、肺、大腸、子宮 頸けい 部、乳房の五つのがんの住民検診を実施する。ただ、2022年の厚労省調査では、五つのがん検診を受けたと答えた人のうち住民検診の受診者は2~4割。残りは健康保険組合や事業所が行う職域検診、個人が自由に選ぶ人間ドックなどで受けており、精密検査の受診勧奨が十分できていないなどの課題があった。
厚労省によると、新たな仕組みの構築は、五つのがん検診別に受診率やがんが疑われた人のうち精密検査を受けた割合を得てがん対策作りに生かす狙いもある。
-
日本睡眠学会(内村直尚理事長)は30日、医療機関が看板などに掲げられる診療科名に「睡眠障害科」を追加するよう求める要望書を厚生労働省に提出した。睡眠に不安を抱える患者が受診する医療機関を選びやすくする狙いだ。厚労省は今後、審議会で追加の可否を議論する方向だ。
要望書では、国内の睡眠医療の課題として、睡眠障害の治療を行う診療科が精神科、小児科、循環器内科など複数にまたがり、受診先がわかりにくいと指摘。医療機関が「睡眠障害内科」「睡眠障害精神科」などと名乗れるようにすることを求めている。
日本小児科学会や日本循環器学会など関連する6学会も賛同している。内村理事長は「子どもからお年寄りまで睡眠に困っている人がいる。早めに受診しやすくすることで、様々な病気を予防できるようにしていただきたい」と話している。
医療機関が看板などで広告できる診療科名は「標榜診療科」と呼ばれ、厚労省が医療法に基づき定めている。「内科」「外科」「小児科」など単独で使えるもののほか、「糖尿病内科」「脳神経外科」など、組み合わせで認められているものもある。それ以外の診療科も開設できるが、路上や駅での広告や看板などで宣伝ができない。
今回、睡眠障害科の追加が認められれば、標榜診療科の見直しは2008年以来となる。
-
難病治療にウコンの力――。三重大学(伊藤正明学長)の研究チームが、消化管の難病の一つ「ヒルシュスプルング病」の手術中の病理組織診断について、ウコンに含まれるクルクミンによる染色を利用した生体深部観察法の新技術「新規生体蛍光観察手法(CVS―IFOM)」を発見した。従来の手法と違って腸管を切除せず、迅速に病変組織を見つけることが可能で、将来的にはがんなどへの応用も期待できるという。(野崎尉)
新たな手法を発見したのは、三重大学大学院医学系研究科個別化がん免疫治療学講座の溝口明特定教授、同研究科消化管・小児外科学講座の問山裕二教授、医学部付属病院消化管小児外科学・小児外科長の小池勇樹准教授らの研究チーム。論文は2024年9月、米国外科学会の公式機関誌で、世界最高峰の外科学会誌「Annals of Surgery」に掲載された。
ヒルシュスプルング病は、消化管のぜん動運動(便を押し出す動き)をつかさどる腸管の神経が先天的に欠損しているため、自分で排便することが難しくなる病気だ。健常者の場合、胎児期にこの神経の細胞が食道から小腸、大腸、肛門へと腸の壁内を移動しながら腸管神経 叢そう (神経のネットワーク)を形成するが、何らかの理由でこの移動が止まってしまうと形成不全となり、発症。病気の型によっては、致死率が15・8~35・5%にも及ぶ。出生約5000人に1人の発症率で、小池准教授によると、「三重大でも多い時には年間3~5例の診断がある」という。
治療には手術が必要で、腸管神経叢の形成が不完全な部分を切除し、形成が良好な部分を肛門とつなぐ。形成が不完全な部分を残したままつなぎ合わせると、術後に重症腸炎の発症リスクが高まってしまうという。現在は、手術中に腸管の一部を切除して、どの部分まで神経叢が形成されているかを診断しているが、小池准教授は「1度の診断で30分から1時間かかり、何度か行うこともあるため時間が取られるし、腸の壁自体を傷つけることになる」と指摘する。
どこで切るべきかを切る前に確実に判断できれば、術後のリスクを含めて患者の負担を減らすことが可能だ。多光子レーザー顕微鏡を使えば、腸管の表面から0・5ミリの深さまでの組織細胞を観察できるが、そのためには細胞を蛍光発色させなければならない。だ
-
暑さが本格化する夏を前に、東京都は熱中症対策をまとめた専用のポータルサイトを新たに開設した。サイトでは、国が発表する「熱中症警戒アラート」をリアルタイムに表示するほか、体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」などの対策もわかりやすく紹介している。
都などによると、都内では昨年6~9月に熱中症で7961人が救急搬送され、同期間の熱中症による死者数は340人に上った。今年も猛暑が予想されていることから、都はサイトを通じて各家庭で早めの暑さ対策を促したい考えだ。
サイトでは、今季は今月23日から発表が始まる熱中症警戒アラートをトップページに表示。水分補給のタイミングや吸水性と速乾性に優れた衣服を着る対策の解説、暑熱順化やエアコン清掃など、暑くなる前からできる取り組みも紹介している。今後は、都内各地の空調設備の整った「クーリングシェルター」の位置なども掲載する予定という。