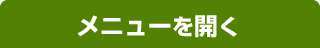-
脊髄の一部がむき出しの状態で生まれ、身体障害などを伴う難病「脊髄髄膜瘤」を胎児の段階で治療する国内初の手術に成功したと、大阪大などのチームが15日、発表した。臨床研究として6例で実施し、多くで症状の改善が見られたという。
脊髄髄膜瘤は、胎児の体ができる途中で脊髄神経が体外へ露出する難病。国内では年間推計200~400人の新生児で見られ、出生直後に手術を行っているが、歩行などに重い障害が出るケースが多い。
海外では2011年、胎児段階の手術で症状を軽減できるという報告が米国であり、欧米を中心に行われているが、産婦人科や脳神経外科など多くの診療科が連携する必要があり、国内の取り組みは遅れていた。
阪大の遠藤誠之教授(産婦人科)らは21年4月~24年4月、超音波検査などで胎児に異常が見つかった6例について、妊娠25週の段階で母親の子宮の一部を切開。胎児の髄膜瘤を修復し、子宮を縫合する手術を、阪大病院などで行った。
5例は既に誕生し、脚の運動機能などに改善傾向が見られたが、1例は合併症により生後3か月半で亡くなった。チームは「手術は成功した」としている。残る1例は出生前という。
今後は保険診療と併用できる先進医療として国に申請し、3年後をめどに保険適用を目指す。
神奈川県立こども医療センターの豊島勝昭・新生児科部長の話「手術の質をさらに向上させるとともに、希望する家族が受けられるよう、情報提供や支援の体制整備も必要になってくるだろう」
-
性感染症の梅毒と2023年に診断された妊婦は383人(速報値)で、この統計を取り始めた19年以降で最多となったことが、国立感染症研究所(感染研)のまとめでわかった。妊婦の胎内で感染した「先天梅毒」の赤ちゃんは、難聴や知的障害などを持つ恐れがあり、感染研は注意を呼びかけている。
感染研によると、23年の梅毒患者は計1万4906人(速報値)で、現在の調査方法となった1999年以降で最多となった。
これに伴い妊婦の患者も増えている。梅毒の診断時に妊娠が確認された人は、2019~21年は年200人前後だったが、22年は267人となり、23年は約1・4倍の383人に増えた。同年は先天梅毒の赤ちゃんも37人(同)と最多を更新した。
梅毒は主に性的接触で感染し、性器や口にしこりができ、全身に発疹がでる。血液検査で感染を調べられる。妊婦の患者のうち75・2%は、診断時には梅毒の症状は確認されなかった。感染していた場合は、抗菌薬で治療できる。
三鴨広繁・愛知医大教授(感染症学)は、「妊婦健診の梅毒の検査では無症状でも発見できるので、確実に受けてほしい。感染していた場合は、速やかに抗菌薬治療を行うことで、母子感染のリスクは減らせる」と話している。
-
鳥取大病院(鳥取県米子市)の村上丈伸助教(脳神経内科学)らが、脳の働きを弱めると考えられている異常たんぱく質「アミロイドβ(Aβ)」の蓄積を従来の方法に比べ痛みを伴わずに検査でき、アルツハイマー病を早期発見できる手法を考案した。Aβはアルツハイマー病の発症10~15年前から脳内に蓄積することから、病気の早期発見・治療につなげられるという。(東大貴)
日本WHO協会(大阪市)によると、認知症の患者数は世界で約5500万人。そのうちアルツハイマー病は約7割を占める。
アルツハイマー病は、まず、蓄積したAβによって脳内のたんぱく質「タウたんぱく」が変化。リン酸化して有毒となったタウたんぱくが脳神経細胞を死滅させ、脳が萎縮して認知機能が低下する。
村上助教は、神経細胞間で情報を伝達し、記憶を定着させる「長期増強」といった現象を、これらの異常たんぱく質が阻害することに着目。痛みを伴わず脳内に弱い電流を起こして長期増強を誘発する「経頭蓋磁気刺激法」という手法を用い、異常たんぱく質の有無による伝達機能の差を調べた。
調査では、軽い物忘れの症状を訴える患者26人の異常たんぱく質の蓄積の有無を検査。それぞれの左頭部に刺激を加え、左大脳がつかさどる右手の筋肉の電位変化を調べた。その結果、Aβが蓄積した患者の多くでは伝達機能が低下したままだった一方、蓄積のない健常者では向上。経頭蓋磁気刺激法が、病気の兆候の確認に有効であることがわかったという。
アルツハイマー病の診断では、痛みを伴う腰への注射が必要な髄液検査や、微量の被曝を伴うPET(陽電子放射断層撮影)検査をして異常たんぱく質を発見しており、新たな手法が確立されれば、体に負担の少ない診断が可能になる。
さらに、脳内からAβを除去するアルツハイマー病の新薬「レカネマブ」の製造販売が昨年、承認されており、こうした手法を用いることで、投薬効果を見極められる可能性があるという。
村上助教は、行方不明になった後、死亡して見つかる認知症患者が多い点に触れ、「この研究から治療法が発達し、認知症に苦しむ方々を支えることができれば。一人でも多くの早期発見・治療につながってほしい
-
順天堂大などの研究者が設立したバイオ新興企業が今月、健康な人の便に含まれる腸内細菌を保管する日本初の「腸内細菌バンク」の運用を開始した。腸内細菌を大腸の病気やアレルギー、がんなどの患者に移植する新しい治療法の開発に役立てられる。担当者は「『健康のお裾分け』にぜひ協力してほしい」と呼びかけている。
人の腸内には、約1000種類の細菌が生息している。細菌の構成バランスが乱れると、様々な病気の発症に影響することが報告されている。そこで、健康な人から提供してもらった便に含まれる腸内細菌の溶液を作り、病気の人の大腸に移植して症状を改善させる治療法「腸内細菌叢移植」が国内外で広がっている。
バンクの運用を始めたのは、腸内細菌移植で腸の難病「潰瘍性大腸炎」などの治療を目指し、順天堂大の研究チームらが2020年に創業した新興企業「メタジェンセラピューティクス」(山形県鶴岡市)。バンクでは、18~65歳の協力者を専用サイトで募集。条件に合った人には、東京都文京区の同大施設で血液や便の検査などを受けてもらい、検査を通過すると、提供者として登録されて便を提供できる。
同社は、2026年までに1000人分の登録を目標にしている。提供者には、研究協力費として数千円が支払われるという。同社取締役の石川大・順天堂大准教授(消化器内科)は「非常に期待がもてる治療法だが、患者さんに届けるためには、腸内細菌の十分な供給が必要だ。今後、国内の複数箇所に『献便施設』を設けるなど、多くの人に協力してもらえるよう工夫したい」と話している。
専用サイトは( https://www.j-kinso-bank.com )。
-
医療用のiPS細胞(人工多能性幹細胞)を患者本人の血液から自動的に作製する技術を、京都大iPS細胞研究財団(京都市)とキヤノン(東京)が共同開発した。iPS細胞の作製費用を大幅に減らせるといい、来年の実用化を目指している。
iPS細胞は血液などの細胞に複数の遺伝子を導入して作製する。患者本人のiPS細胞を作り、筋肉や神経などの細胞に変化させれば、移植しても拒絶反応が起きにくく、免疫抑制剤を使う必要がない。病気やけがで失われた体の組織や機能の再生が期待できる。
ただ、従来の手作業での作製では専用施設の整備や維持、技術者の人件費などのコストがかさみ、1人分の作製に約4000万円かかるとされる。
キヤノンなどが開発した方法では、血液から赤血球など不要なものを取り除き、残った細胞に遺伝子を導入。できたiPS細胞を増やして回収するまでの約20日間の工程を自動化する。
全自動の装置が完成すれば、人の手が必要なのは血液や試薬のセットと、iPS細胞を回収した容器を取り出す作業だけとなり、品質の安定につながるという。臨床試験などを行う大学や企業に対し、作製したiPS細胞を提供し、患者に移植することを想定している。
財団は、患者本人の細胞から医療用iPS細胞を短時間に安価で作製する「my iPSプロジェクト」の一環として、この技術開発を進めており、1人あたりのコストを「100万円程度」に下げる目標を掲げる。キヤノンメディカルシステムズ研究開発センターの山口陽介さん(45)は「できるだけ早く患者由来のiPS細胞を作り、治療に生かしたい」と話している。
-
膵臓の細胞が正常に働かない1型糖尿病患者に、ブタの膵臓組織「 膵島すいとう 」を移植する臨床研究を、国立国際医療研究センターなどのチームが来年にも実施する計画であることがわかった。移植した組織から血糖値を下げるホルモンがつくられ、注射治療が継続的に必要な患者の負担軽減につながる可能性がある。実用化すれば、移植用の臓器不足の改善が期待できる。
人とサイズが近いブタの臓器や組織を人に移植する治療法は「異種移植」と呼ばれ、次世代の医療として注目されている。国内で腎臓や心臓などの病気に対して複数の移植計画があるが、実施例はない。
同チームの計画では、生後2~3週間のブタの膵臓から、血糖値を下げるインスリンホルモンを分泌する細胞の塊「膵島」を取り出す。人に移植したときに起こる拒絶反応を防ぐため、直径0・5~1ミリ・メートルの特殊なカプセルで1~3個程度の膵島を包む。
そのうえで、数十万個の膵島を1型糖尿病患者の体内に移植して壊れた細胞の機能を代替させる。カプセルには微小な穴があり、血糖値の上昇に合わせてインスリンが放出されると期待できるという。移植手術は、国の認定を受けた委員会などの審査を経て来年にも実施する。
死亡した人から提供された膵島を患者に移植する治療は2004年以降、国内でも行われているが、提供者(ドナー)不足が課題だ。ブタの膵島を使った異種移植も1990年代からニュージーランドなどで行われ、一定の有効性が確認されているが、細胞の加工設備などに課題があった。
同センターは2019年、移植する膵島を免疫細胞の攻撃から守るカプセルで包む製造施設を整備した。霜田雅之・膵島移植企業連携プロジェクト長は「免疫抑制剤を使わないで済む可能性が高く、体への負担も軽い。インスリン注射なしで生活できる治療を目指したい」と語る。
他にも、神戸大や福岡大などもブタの膵島移植の実用化に向け研究を進めている。04年に人の膵島移植を国内で初めて行った松本慎一・神戸大客員教授は、「ブタのインスリンは、薬として広く使われてきた歴史があり、十分な効果が見込まれる」とみている。
日本膵・膵島移植学会理事長の剣持敬・藤田医科大教授
-
次の感染症危機に備える新たな専門家組織「国立健康危機管理研究機構」(日本版CDC)について、政府は2025年4月に設立する方針を固めた。9日に開く準備委員会で方針を提示する。設立時期はこれまで「25年度以降」としていたが、感染症への対応を強化するため、できるだけ早期の体制整備が必要と判断した。今後、閣議で正式決定する。
新機構は、米疾病対策センター(CDC)をモデルとし、病原体などを研究する国立感染症研究所と、感染症の治療などにあたる国立国際医療研究センター(NCGM)が統合して発足する。昨年の通常国会で関連法が成立した。
今年1月からは、厚生労働相直轄の準備委員会を設置し、専門家らが組織体制などについて検討を進めてきた。
指揮命令系統を効率的に機能させるため、統括部門として「危機管理総局」を設置する。平時から国内外の感染症に関する情報を収集し、状況を早期に把握。有事には、〈1〉海外で新たな感染症が発生したとき〈2〉国内で感染者が確認されたとき〈3〉国内で流行したとき――の段階ごとに、致死率や感染力など、どれほど危険な感染症かを評価する。このリスク評価の結果を踏まえ、対策にあたるチームを編成する。
今後は、25年4月の設立に向け、政府内で新機構のトップとなる理事長の人選や、人員規模などの検討を急ピッチで進める。
日本は新型コロナウイルスへの対応が後手に回ったが、感染研とNCGMが統合すれば、基礎研究から診療までの一体的な対応が可能になり、未知の病原体に対する初期対応が迅速化されると期待される。
海外と比べて遅れたワクチンや治療薬の開発でも、新機構は国内外の病院との連携を強化し、中核的な役割を担う方針だ。
-
血液に含まれる分泌物質内の「ガレクチン10」と呼ばれるたんぱく質が気管支ぜんそくの診断や進行の予測に活用できることを確認したと、大阪大などのチームが発表した。従来の診断方法より精度が高まるといい、数年後の実用化を目指すとしている。論文が国際医学誌に掲載された。
気管支ぜんそくは空気の通り道である気管支が慢性的に炎症を繰り返すことで狭くなり、呼吸困難などの発作が生じる病気。世界保健機関(WHO)などによると、世界の患者数は2億6200万人、国内では推定で1000万人とされる。血中の白血球の一部「好酸球」の量などで診断しているが、肺の機能が低下する「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」との区別が難しいなどの課題があった。
阪大の武田吉人准教授らは、採血で得る血液中の分泌物質「エクソソーム(細胞外小胞)」が体内の情報を伝達している役割に着目。エクソソームを解析し、含まれる約3000種類のたんぱく質とぜんそくとの関連を調べた。
その結果、炎症などに関わるたんぱく質のガレクチン10の量が増えると、ぜんそくの傾向が強いことを確認。診断の精度を調べると好酸球の73%に対して80%に高まったという。
気管支ぜんそくに詳しい佐野博幸・近畿大教授の話「重要な研究だ。ガレクチン10の量に応じて適切な薬が選べるようになれば、治療の効率化につながる」
-
【花蓮(台湾東部)=園田将嗣】台湾東部・花蓮沖を震源とする地震は6日、生存率が急激に下がるとされる「発生から72時間」が過ぎた。震度6強を観測した花蓮では、消防や軍の捜索救助活動で3人の遺体が見つかり、地震による死者は13人となった。負傷者は1147人で、オーストラリアの旅券を持つ外国人2人を含む6人が行方不明となっている。
消防当局によると、有名観光地の太魯閣渓谷沿いの歩道で崖が崩落した現場で5日から6日にかけ、岩の下敷きとなった3人の遺体が発見された。近くには他に3人が埋もれているとみられる。余震が相次ぎ、現場に向かう道路状況も悪いため、捜索救助活動は難航している。
渓谷沿いにあるホテルなどには、6日夕時点で398人が取り残されている。寸断されていた渓谷から西側につながる道路で小型車の通行が可能となり、孤立した状態の解消が期待されている。6日夜には、無人機(ドローン)を扱うトルコの捜索隊が花蓮に到着する予定で、捜索救助活動に加わる予定。
衛生当局によると、花蓮や北部の新北市などで被災した404人が避難所に身を寄せている。
-
急激に重症化する「劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)」の患者数が、過去最多だった2023年を上回るペースで増えている。国立感染症研究所は2日、今年は3月24日までに556人が報告されたと発表した。前年同期の2・8倍に上っている。
都道府県別では、東京が89人で最も多く、埼玉(42人)、神奈川(33人)、愛知(31人)が続く。23年は941人(速報値)で最多となったが、今年はすでにその半数を超えている。
STSSの原因となる「溶血性レンサ球菌(溶連菌)」は、ありふれた細菌で、子どもの咽頭炎を招くA群溶連菌がよく知られている。通常は風邪の症状で済むが、まれにSTSSを発症する。
急増する要因ははっきりしないが、感染研が患者126人から検出した菌を調べたところ、病原性と感染力が強いとされる菌のタイプが34%を占めていた。